吉方位にある心と体を気持ちよく潤してくれる開運スポットへの旅行計画がおすすめです。
心と体を気持ちよく潤してくれる開運スポットは、水辺、水族館、博物館、美術館、見晴らしがよい場所です。
見晴らしがよい場所は、心をリフレッシュさせる絶好の開運スポットです。
吉方位旅行
吉方位旅行は目標地までの移動運動です。
移動運動を繰り返し行うことで風水パワーを高めることができます。
風水では日常の移動行為を含む旅行で年、月、日、時間のうちどれかが重なると吉方位旅行の吉方位になり、重なりが多くなるほど風水パワーが強くなると言われています。
新月の日と満月の日でも風水パワーが変わります。
年、月、日、時間の吉方位と新月の日と満月の日を組み合わせることで、吉方位の予測や振り返り、吉方位旅行の計画と反省を行うことができます。
吉方位の起点
吉方位は太陽の位置と起点を結んだ方位です。
目的を実現しようと考えて出発する場所が吉方位旅行の起点になります。
年、月、日、時間の吉方位の重なりが多い方位を選んで目標地を決めます。
水辺
水辺は心と体を気持ちよく潤してくれる、吉方位旅行の開運スポットです。
水辺には砂浜、岩場、干潟、藻場、葦原、河畔林、渓畔林、マングローブ林、塩性湿地、汽水域など多様な環境が含まれます。
水辺の水性植物は水質浄化機能をもっていたり、生物にとっての生息空間になったりするなど、自然環境を維持する上で重要な役割を担っています。
砂浜
砂浜は海に最も近くで接することができる開運スポットです。
九十九里浜
九十九里浜は目の前に太平洋が広がる東から昇る朝日に近い砂浜です。
浄化のパワーがあり過去の清算をしてやる気と活力が得られる開運スポットです。
海

風水では海は浄化のパワーがある開運スポットと言われています。
海は陸地以外の部分で海水に満たされたところです。
海には微生物から大型の魚類やクジラ、海獣まで膨大な種類・数の生物が生息しています。
海水
海水には塩を主成分とするミネラルなどが概ね3%含まれています。
海水の動き
海水面の高さは毎日2回(年に数回、1日1回の日がある)上下に変化(潮の満ち干(かん))します。
灯台
灯台は岬の先端や港湾内に設置されています。
夜間に船を誘導するために使用されます。
船
船は人や物などを載せて水上を移動する目的で作られた乗り物の総称です。
船は浮揚性、移動性、積載性の三要素を全て満たす構造物です。
川
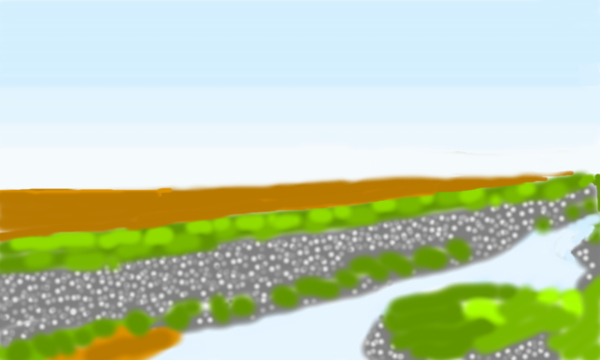
川の構造
本流に各地から集まってきた支流が流れ込む樹状構造です。
川の流速
川の流速は川全体の勾配に比例していて、源流の標高が高く川の長さが短いほど流速が速く急流です。
川況係数
川の最小水量と最大水量の差を川況係数と呼び、川況係数が大きいほど渇水期と雨季の流量の差が激しく治水や利水が困難になります。
川の水収支
水収支は1年以上の長期をとればほぼ釣り合います。
短い期間の量の増減と収支のバランスは日々の天気や季節変動に大きく左右されます。
湖沼(こしょう)
湖沼は周囲を陸に囲まれ海と直接連結しない水域です。
火山が成因の面積1㎢を超える日本の湖
北海道地方:阿寒湖(あかんこ)、屈斜路湖(くっしゃろこ)、俱多楽湖(くったらこ)、然別湖(しかりべつこ)、支笏湖(しこつこ)、知床五湖(しれとこごこ)、洞爺湖(とうやこ)、摩周湖(ましゅうこ)
東北地方:十和田湖(とわだこ)、秋元湖(あきもとこ)、小野川湖(おのがわこ)、沼沢湖(ぬまざわこ)、桧原湖(ひばらこ)
関東地方:中禅寺湖(ちゅうぜんじこ)、榛名湖(はるなこ)、芦ノ湖(あしのこ)
中部地方:河口湖(かわぐちこ)、西湖(さいこ)、本栖湖(もとすこ)、山中湖(やまなかこ)
九州地方:池田湖(いけだこ)
宍道湖(しんじこ)
宍道湖は出雲市と松江市にまたがり、真水と海水が混ざり塩分が含まれる弱汽水湖です。
しじみや多種の魚類が生息しています。
沼
沼は浅い水底でその全面で水生植物(沈水植物)の生育が可能な水域です。
水場
水場は
- 登山で飲み水の確保できる場所
- 野獣や野鳥が水を飲みに集まる水辺
- 土地が低く直ぐに水の出る所
などです。
池
池は掘って水を貯めた所です。
庭園や公園の要素の1つとして作られるものや、何らかの実用的な理由で水を貯めておくために作られているものなど、様々なものがあります。
井戸
長野県松本市の槻井泉(つきいずみ)神社の湧水、源智(げんち)の井戸、鯛萬(たいまん)の井戸で調査が行われました。
槻井泉(つきいずみ)神社の湧水は、水神が祀られ、湧水があって、公民館が併設するこの空間一帯が地域のシンボル的な場所です。
源智(げんち)の井戸は、松本市特別史跡で文化財で観光地化されています。
鯛萬(たいまん)の井戸は水を汲みにくる人の大半が近隣住民です。
「槻井泉(つきいずみ)神社の湧水」と「鯛萬(たいまん)の井戸」が地域の憩いの場として機能していました。
水辺へGO!
日本初!水辺(川、湖、池)だけのデータを集めるアプリです。
調査結果の見える化
地図上の水辺スポットの色や、レーダーチャートの形、写真等で水辺のすこやかさを視覚的に知ることができます。
水辺データの共有
みんなが調べた日本や世界の水辺を見ることができます。
自分が調べた水辺をマイデータに集められます。
スマホ1つで水辺を調査
水辺は、川や湖、池、沼等、水のある場所です。
海や人工的な池は対象外としています。
アプリを使って5つの視点からなる質問に答えるだけで水辺の調査ができ、「水辺の見方」を学ぶことができます。
5つの視点は、環境省が策定した水辺のすこやか指数を活用しています。
水辺のすこやかさ指数は川などの水辺の見方を表す指標体系で、5つの視点から成り立っています。
「自然のすがた」「豊かな生き物」は自然環境(緑色)を表し、
「水のきれいさ」「快適な水辺」「地域とのつながり」は人間活動(ピンク色)を表します。
自然環境と人間活動のバランスがとれていることが大切です。
各視点の平均点を五角形のレーダーチャートに表し、五角形の形が大きくかつ正五角形に近いほど、「すこやかな水辺である」と判断します。
調査記録が重要な資料に
集まった水辺データ(調査結果、写真、コメント)はアーカイブされ、水辺整備(環境計画や防災・減災計画)の参考として有益な資料になります。
水族館
水族館は、主として海や河川・湖沼などの水中や水辺で生活する生物(水族)を展示・収集している施設です。
水族館では魚介類や無脊椎動物、両生類、海獣類、爬虫類といった動物や、水草などがガラスやプラスチックの透明な水槽に入れられて公開されています。
世界の水族館の総数は2010年代初頭において約500館と推定され、うち2割が日本に立地すると言われています。
- 水槽用の水・餌となる生き物の確保が簡単で、低コストで済む
- 水辺に暮らす生き物の調査・研究がしやすい
- 海の近くの方が景観的にも良い
などの理由から水族館は水辺に近い所に立地している場合が多いです。
博物館
博物館は特定の分野において価値のある学術資料、美術品等を購入や寄託・寄贈などの手段で収集・保存し、それらについて専属の職員である学芸員が研究すると同時に、来訪者に展示の形で開示している施設です。
文化財を含む貴重な資料の保存・修理や、研究とその成果を公刊する役割も担います。
自然史、歴史、民族、民俗、美術・芸術、科学・技術、交通(鉄道や自動車、海事、航空)、軍事・平和などのうち、ある分野を中心に収蔵・展示している博物館が多いです。
絵画や彫刻などに重点をおく施設は美術館と称します。
文化だけでなく観光資源としても大きな役割を担います。
美術館
美術館は博物館の一種で、美術作品を中心とした文化遺産や現代の文化的所産を収集・保存・展示し、またそれらの文化に関する教育・普及・研究を行う施設です。
美術館は博物館の一形態という性質上、観収蔵品の蓄積が展示と並んで重視されます。
大阪中之島美術館
会期:2024.11.16 – 2024.12.15 月曜日休館
Osaka Directory 7 Supported by RICHARD MILLE 小松千倫(こまつ・かずみち)展
「Osaka Directory 7 Supported by RICHARD MILLE」は、大阪中之島美術館が関西・大阪21世紀協会と共同で主催する、関西ゆかりの若手作家を中心に個展形式で紹介する展覧会です。
将来活躍が期待される関西の若手アーティストの情報を美術館というディレクトリに格納・保管し、大阪中之島美術館から広く世に紹介し世界に羽ばたくことを支援します。
概要
1970年の大阪万博は音響システムや野外ライブが普及するきっかけの一つと言われており、「せんい館」でも音と映像を用いた前衛的な展示が行われました。
1970年の大阪万博のパビリオン「せんい館」から着想を得て、今回小松は音とともに集い離散する人々の在り方を「ソフトレイヴ」と呼び捉えようと試みます。
大阪の文化史と千里丘陵や淀川水系といった地形を重ね合わせつつ考察し、鑑賞者のための空間を生み出します。
見晴らしがよい場所
山手台東5丁目きんもくせい公園
きんもくせいの花壇や遊具が設置されていて、美しい夜景を見ることができます。
山手台北公園
宝塚山手台の街並みはもとより大阪から神戸方面の景色が一望できます。
夜はライトアップされた大阪国際空港の滑走路も眺められます。
大阪府民の森 なるかわの森
大阪府東大阪市上六万寺町1748-2
なるかわの森の広さは204haです。
ハイキングや自然とのふれあいの場、癒しの場、クラフトなど創作の場として利用されています。
展望休憩所が用意されている登山道で、道幅が広く勾配は8%と緩やかです。
大阪平野はもちろん、天気がよければ淡路島や六甲山までを一望できます。
展望台
展望台は、岬の先端や山の頂上付近、あるいは高層建築物や塔の最上階にある、景色を見るために設置されている設備です。
塔(tower)
塔は床面積が少なく延べ床面積が大きい高層建築物です。
展望塔や電波塔などがあります。
塔は視線を引き付けます。
電波などの中継地点になる塔には強いパワーがあります。
自然公園(地域制公園)
地域制公園は自然公園法に基づく自然公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権限に関係なく、その区域を公園として指定し土地利用の制限・一定行為の禁止又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的としています。
自然生態観察公園(アーバン・エコロジー・パーク)
都市化の進展による自然環境の減少に伴い、都市内において野鳥等の小動物と接する機会が減少している一方、野鳥や昆虫等と身近にすることへのニーズは年々増加しています。
都市内において小動物のオアシスとなるべき質の高い緑地環境の保全創出を図る必要から、都市に自然を呼び戻し人間と生物が触れ合える拠点整備を目的とした公園です。
高原
中緯度地帯の高原は夏季でも冷涼であり高冷地と呼ばれます。
涼しい気候を利用して、レタス、キャベツ、白菜、大根などの野菜の抑制栽培が行われています。
育つのが遅くなるため高原野菜と呼ばれ、他の地域で生産されたものが出回って少なくなった頃に出荷されます。
夏季でも冷涼であるため避暑地としても利用されています。
冬にはスキー場となる所も多いです。
特に東京から比較的容易に行ける長野や山梨にも沢山の高原があります。
高原と言えば「夏に涼しく快適に過ごせる場所」というイメージがあるかもしれませんが、実は年間を通して楽しみ方は様々です。
伊豆高原
伊豆高原は、静岡県伊東市の対島地区の大室山南東方面(富戸・池・八幡野)を伊豆急コミュニティーが開発した温泉付き別荘地です。
首都圏からのアクセスが比較的容易であるうえ、海や山の自然が近くにあります。
伊豆高原の地理
伊豆高原の地域は伊豆半島の東岸、伊東市の中南部に位置し、南西側に天城山の裾野が続きます。
伊豆東部火山群の溶岩流などで形成された丘陵地に発展しています。
相模灘に面する海岸線までを含めて「伊豆高原」と呼ばれています。
